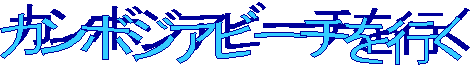

☆アンコールワットのないカンボジア
「しょうがないやろ。俺はアンコールワットには何の興味もないんやあああ!」となんど叫びたかったことか。
僕はそのころ、カンボジアをうろついていた。『のまど』の「あなただけの旅物語賞」にラオスの愚かなエッセイを出したところ、なぜか優秀賞をもらってしまい、その商品5万円旅行券をもってかの地をさまよっていたのだ。
〃カンボジア旅行業界〃には前から不満があった。なぜ、カンボジアと言えばアンコールワットなのか。まるで〃日本=ゲイシャフジヤマハラキリ〃というのと同じ図式ではないか。
実際、僕は2000年末にほぼ1ケ月にわたってこの国を旅したが、このような人は少数派だった。と言うより、ほとんどいないのだ。たいていの人は、アンコールのあるシェムリアプと首都のプノンペンを訪れただけで、あっさりと数週間で帰ってしまう。中には、アンコールだけ見て帰ってしまうような不届き者もいる。
僕は旅行に行く前、ある雑誌のカンボジア特集を見ていた。そこにはアンコールワットの写真は載っていたのだが、カンボジアの人々は写っていなかった。どうやら、カンボジアには人間が住んでいないらしい。
もちろん、そんな馬鹿な話はない。彼らにカンボジアの人々の姿が見えなかっただけである。アンコールにしても、遺跡に興味がない者には何の意味もない存在だ。僕は、退屈な遺跡と猥雑な首都に背を向け、バスに飛び乗った。目指すは、シハヌークビルという街のビーチだ。
そう、カンボジアにはビーチがあるのだ。僕は、カンボジアの南端にあるこの街についてレポートしたい。この街についてはガイドブックには載っているが、本格的に紹介されたことはまだない。カンボジアはアンコールだけではないことが分かると思う。素敵な男は、遺跡に行かない。シャイな男は、ビーチを目指す。
☆シハヌークビルへ
さて、僕はプノンペンから1200リエル(約300円。1ドル=約3900リエル)のバスに乗りシハヌークビルに向かった。本当は優雅に鉄道で行きたかったのだが、カンボジアの鉄道は危ない。僕が滞在している間にも、プノンペンで反政府ゲリラのテロがあり、線路で地雷が爆発したかとで不通になっていた。なかなかおもしろい国だと思うが、しょうがない。僕は涙を飲んで、散文的なバスを選んだのだった。
バスは、カンボジアとしては信じがたいほど滑らかな道路を行く。何と、この道は舗装されているのだ。シェムリアプ=プノンペン間の「地獄の黙示録」のような道路を経験していた僕にとっては、それだけでも感動ものだった。途中でスコールに見舞われる。だが、それがまたこれから行くビーチの雰囲気を盛り上げてくれる。
そうだ、海だ。僕らの前方には、ビーチが輝いているんだ!
僕は勝手に興奮しながら、バスのシートから腰を浮かせていた。 バスはシハヌークビルの市内に入った。そのとき、僕は異様な光景を目にした。
何台ものバイクが、叫び声をあげながら僕らのバスについてくるのだ。
バスは街の中を進んでいく。それにしたがい、伴走するバイクの数もますます増えていった。バスターミナルに着くころになると、その数は数十台にのぼっていた。
バスが止まった。ドアが開き、降りようとする僕は言葉を失った。降りられないのだ。
バスの入り口には数十人もの男たちが群がり、何事か叫んでいる。彼らはカンボジアによくいるバイクタクシーの運転手で、客を求めてバスの入り口に群がっているのだ。アジアにはよくある麗しき光景だが、カンボジアではお目にかかったことがなかった。だいたいカンボジア人はがっついてなく、おとなしいからだ。だが、ここはなにやら分からないが燃える闘魂とガッツに満ちたピキピキバリバリの熱い無法地帯らしい。
ここはシェムリアプやプノンペンとは少し違う。僕はそう思いながら、人に揉まれて無理やりバスを降りた。運転手連中としばし熱き交渉をした後、今日泊まるゲストハウスに向かう。僕の胸の中には、すでにビーチが広がっていた。
ゲストハウスに荷を下ろした僕は、すぐさま外に飛び出した。本当は長いバス旅行で疲れていたのだが、飛び出さざるをえなかったのだ。バイタクを急いでつかまえ、こう叫ぶ。
「どこでもいい。俺をビーチに連れてってくれ!」
ほとんど青春ドラマの主人公のセリフだが、僕は真剣だった。街の雰囲気が、そうさせたのだ。しばし熱き交渉をした後、ビーチに向かう。むこうに着くと、もう日は暮れかかっていた。もう泳ぐ人もなく、人々は帰り支度をしている。そのいわば「用済み」の海、人間がいなくなった後の裸の海に、陽が落ちる。黄金の輝きが広がり、水の上でダンスを踊る。僕はその水面の動きに、しばし見とれていた。
そのうち、星が出た。月が遠く水平線上で輝き始めた。帰りも僕を乗せて行こうと待ち構えていたバイタクの運転手も、いつの間にかいなくなっていた。
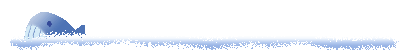
☆ビーチへ行く
翌朝。僕は〃サムズ・ゲストハウス〃というほとんど掘っ建て小屋のような宿で目を覚ました。目が覚めるなり、僕は訳の分からないカンボジア・ポップスの響きに包まれていた。隣の家から流れてくる音楽だった。
「やるなあ……」と僕は思った。何がやるのかは分からないが、なんだか街全体がそうやって僕を歓迎してくれているような気がしたのだ。僕は気をよくしてベッドから起き上がった。
今日はビーチに行かなくちゃ……と思うのだが、積極的に動き回る気力をすっかり失っていた僕だった。ここはえらくのんびりした街なのだ。もともとカンボジアは日本やタイよりのんびりした国だと思うが、この街ののんびり度は群を抜いている。同じカンボジアのシェムリアプ、プノンペンを抜いて、堂々の一位と言えよう。 昨日は、宿を決めるだけで大騒ぎだった。最初に行った〃メリ・チェンダ〃というゲストハウスでは、宿のマダムが部屋の鍵を探してくるだけで30分かかった。僕は正直言ってこの宿には泊まる気がなかったので、血相を変えて鍵入れのカンの中を探しまくるマダムに対して、「いいかげんにしてくれ。俺はこの宿には泊まらんのやああ!」 と叫びそうになった。その後行ったもう一つのゲストハウスでも、鍵を探すのに50分くらいかかったので、これはこの街の人の共通の弱点なのかもしれない。
その後の夜に行った、「タイ・マレーシア・ジャパニーズレストラン」 という不気味な食堂でも、事態は同じだった。店先には、女の子が5人、暇そうに座っていた。僕が店に入ると、あわててメニューを持ってくる。カバーのついた立派なメニューなのだが、中にはメニューは一枚しか入っていなかった。しかもそこには、堂々と〃ブレックファースト〃と書いてある。おいおい、夜からブレックファーストを食わせるつもりかい。
俺は〃ジャパニーズ・フード〃を食べたいんだ。そう僕が冷静に告げると、女の子は急いで新しいメニューを持ってくる。開く。そこにはまた、〃ブレックファースト〃しかなかった。僕がふたたび冷静にその事実を告げると、あわててもう一つのメニューを持ってくる。そこにもやっぱり、〃ブレックファースト〃しかなかった。おいおい、この街の人々は、朝飯しか食わんのかい。
結局、まともなメニューが出てくるまで、またもや30分かかったのだった。そしていざフル・メニュー、魅惑の日本料理メニューが出てきたかと思うと、そこには「ヤサイ・サラダ」「ガーリック・テッパン」などという不気味なものしかなく、すっかり食欲はなくなっていたのだった。
さて、ここで何の話をしているかと言うと、僕がビーチに行くという話である。
シハヌークビルにはビクトリービーチ、インデペンデンスビーチ、ソカビーチ、オーチディルビーチなどいくつものビーチがあるが、僕が到着の日に夕陽を見に行ったのが、一番人気のあるソカビーチである。今日もそこに行ってみることにした。
ゲストハウスから少し離れた所から、バイタクをつかまえる。このシハヌークビルのバイタクは、激しくぼる。それでもむりやり2000リエルという適正価格(たぶん)にして、ソカまで行く。
バイクは風を切って進んでいった。しばらく行くと、高台にさしかかった。
そのとき突然、視界が開けた。
そこにはシハヌークビルの海が、キラキラと美しく情熱的にまたたいていた。なんだか、期待が高まってきた。
ビーチに着く。バイクから降り砂浜の上を歩きだすと、僕はある奇妙な感覚に襲われ始めた。なにかが違う。しばらく歩いてみて、その理由が分かった。
砂が〃啼いて〃いるのだ。
そう、シハヌークビルの砂浜は啼くのである。僕はそれだけで、うれしくなってしまった。なんとなく、足元からゴージャスな感じがしたのだった。
砂が啼けば、王侯貴族だ。
僕はキュッキュッという砂の響きを楽しみながら、ビーチに降り立った。そこには、鮮明に白い砂浜と青く淡い海とが広がっていた。 シハヌークビルの海の魅力は、それが〃普段着〃である、という事にある。けっして派手ではないが、どこかの海みたいにギンギンギラギラのわざとらしさがない。それは、素顔の海なのだ。
ちょうど、さりげないが何となく気になる近所のきれいなお姉さん、という感じか。なんとなくそばにいてほしい海、という感じだろうか。
そして、素顔のままが美しい。僕は静かに、波打ち際で足を浸していた。
ソカビーチは、特にカンボジア人に人気がある。あちこちに地元の人々を乗せて来たワゴンが止まり、海の家がある。パラソルがひるがえり、デッキチェアーがある(一人1000リエル)。
次から次へと頭にザルを載せた物売りがくる。ジュース売りが来る。ロブスター売りが来る。ビーチにおける世界的現象として、彼らのふっかけはかなりきつい。ビーチに泳ぎに来る奴は暇などうしょうもない奴、という偏見があるのだろうか。なかなか正しいような気がするが……。
……などと言いながらも、僕は暑さに参ってきた。ここはプノンペンやシェムリアプに比べても、格段に暑いのだ。僕はすばやくデッキチェアーに座り、ビーチの人になることにした。
海を渡る風が吹く。はるか水平線上には船影がゆらめく。
子供たちの笑い声。波の響き。ときどき聞こえる船の汽笛。
その日、僕はそうやってまた、夕暮れ近くまで海のそばにいたのだった。
さて、一番客の多いソカビーチだが、シハヌークビルのビーチはもちろんこれだけではない。
ほかにも少し岩が多いが風情のあるインデペンデンスビーチ(名前がすばらしい)、人は少ないが素朴で美しいオーチディルビーチなどがあるが、ここで僕はもう一つのビーチを推奨しておきたい。
実を言うと、バックパッカーたちはソカビーチにはあまり行かない。いや、行くのかもしれないが、圧倒的なカンボジア人の群れの中に埋没してしまっている。
バックパッカーが行くビーチ、それは〃ビクトリービーチ〃をおいてほかはない。
ここにはバックパッカーを魅きつけるなにかがある……というのならおもしろいが、実際にはそういう事はなく、ただ単にシハヌークビル唯一のゲストハウス村に近い、というだけの理由なのだが、ここがなかなか趣があるのだ。
ここには、ソカビーチの壮麗さも開放感もない。きわめてこじんまりとした、地味なビーチなのだ。
砂浜の広いソカからくると、その狭さに驚かされるだろう。ちょうど4畳半ぐらいの大きさなのだ。それはちょっとおおげさだが、ちょうど猫の額ぐらいの大きさの砂浜に感激する。
客もほとんどいない。ここにぽつねんと座っていると、なんだか無人島に漂流したような気分になってくる。
寄せてくる波の響き、そして流れ寄る椰子の実ひとつ、水平線上を行く船の影……なんとなく切なくなってきて、思わず人生やら世界の不条理、人間の悲しみなんかについても考えてしまう。
ここに来ると、だれでも哲学者になってしまう。
ま、実は隣で太った白人パッカーがだらし無く腹を出して寝転がったりしているのだが、そこがまたロビンソン・クルーソーの気分を盛り上げてくれる。波の響きも哲学的だ。
僕は毎日ここに通い、ひとり悲しみにふけっていたのだった。
☆シハヌークビルな日々
さて、人間はいつまでも海の中にいる訳には行かない。必ず、散文的な日常へと戻って行かねばならない。昼の裏側には常に影がある。という訳で、ここでシハヌークビルの街の様子について書いてみたい。
僕がシハヌークビルに着いたとき、まず気づいたことは、「言葉のメロディが変わった!」ということだ。
僕はクメール語は一言も分からないが、そんな僕でも言葉の色合いが変わったのが分かった。どちらかというと少し鋭い響きのあるプノンペンの言葉に比べ、よりゆるやかで、のんびりしたメロディになったのだ。
それとともに、人の気質も変わった。
忙しく、どちらかというと剣のあるプノンペンの人々と比べ、こちらの人々はよりフレンドリーだ。街で目が会うと、気軽にほほ笑んでくれる。なにかれと話しかけ、世話を焼いてくれる。
それにしても、こんなに人々が働かない街も珍しいのではないかと思う。街を歩いていてすぐに気づくのが、異常なまでのハンモック消費量の多さだ。そこかしこで揺れている。一度市場に行くと、そこには物売りのおばはんたちが10人、商売を全くせずに延々とハンモックで揺れているだけ、という壮絶な地帯があった。日本のハンモック業界は、シハヌークビルを標的にすべきだと思う。ハンモック消費量は、おそらく世界一である。
バイタクの多さにも参る。正直言って、ここの男は全員バイタクの運転手ではないか、と思うほどだ。
おそらく、客1人につきバイタクは50人ぐらいいると思う。それにしても不思議なのは、これほど商売としては不利な状況にありながら、奴らが一向に値引きしようとしないことだ。
ここのバイタクは激しくぼる。というよりここは観光地だから全般的に物価が高いのだが、バイタクはそのすべての上を行っている。 相場0.25ドルぐらいのところを、平然と「2ドルだ!」と言ってくる。僕があほらしくなってその場から立ち去るそぶりを見せても、追って来ない。ほかの地域なら、「おお、悪かった。俺のバイクに乗ってくれ!」と追いすがってくる、可愛いところがあるのだが……。
おそらく、ここの連中は働かなくても食っていけるのだろう。バイタクをやっているのも、暇で暇でしょうがないから暇つぶしにやっているのに違いない。それにしても奴らはろくに街の道も知らず(むしろ僕のほうが知っているのではないかと思う)、それでも平然とぼろうとするのだから、立派だ。なんでこんな連中が存在しているのか、不思議なくらいである。
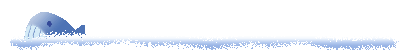
☆ゲストハウス村の天使
前述のように、シハヌークビルは観光地だから、物価は少し高い。ゲストハウス村には地元の人が食べるような食堂はほとんど存在せず、筋金入りのバックパッカーからは軽蔑される「外国人食堂」にある程度頼らざるを得ない。
だが、僕はその外国人食堂に〃天使〃を見つけたのだ。
ある夜のこと。僕は空腹を抱えてゲストハウス村をうろついていた。すると、月明かりの中に奇妙な手書きの看板が浮かび上がっていた。そこには、こう書いてあった。
「日本人来て来て。やすくておしい」
う、あやしい……。僕はなんとなく嬉しくなって、その一軒の食堂に入ったのだった。
すると、一人の小柄な女の子が現れた。鼻筋の通った、インド系の顔立ちの小さな女の子。
僕がメニューを見て注文すると、その娘は「だいじょうぶ。ちょっとまって」と明るく日本語で言って、笑って立ち去ったのだった。 後で聞くと、彼女はサンちゃんといい、12歳。表のメニューも彼女が書いたのだという。彼女の日本語はたどたどしく、「だいじょうぶ。ちょっとまって。ありがとう。どいたしまして」ぐらいしか言えなかったが、そこがまた可愛らしく、ここに来る客(西洋人が多い)の間で人気者になっていた。彼女はお姉さんのリナちゃん(15歳)とこの店を切り盛りしていた。そして、この店はこの周囲の外国人食堂では一番安かったのである。味も悪くはなかった。 このサンちゃんの魅力に参ってしまっている日本人もいた。「サンちゃんを日本に連れて帰りたいっすよ」とちょっと危なげなトール君は言う。一方、巨漢のトラゾーは「サンちゃんが好きだあ!」と夜の星に向かって叫ぶ始末。全く、何をやってんだか。
この姉妹は聡明で、日本人客の誘致に熱心だった。今、このシハヌークビルには日本人はほとんどいないが、今にここが日本人旅行客の溜まり場になるかもしれない……。そう感じた僕は、一冊のノートを買いに走った。おもむろにペンを取り出し、表紙にこう書きつけた---「サンちゃんノートvol.1」
そう、これは情報ノートなのである。恐らくこれは天地開闢以来、シハヌークビル史上初めての日本語情報ノートになるはずだ……そう考えて僕は〃サンちゃんレストラン〃に持って行った。サンちゃんのお母さんは、とっても喜んでくれた。
という訳で、このノートは破棄さえされてなければ、今もサンちゃんレストランにあるはずだ。当地を訪れた方は、ぜひ見ていただきたいと思う。
カンボジアはアンコールワットだけではない。それ以外にも人間の悲しみがあり、喜びがあり、海があり山があり、そして星があり空があるのである。僕らが心を閉ざしさえしなければ、それは見えるはずなのだ。
それでは、皆さんにもよい旅を---。
《シハヌークビル・データ》
プノンペンからバスで約3時間、12000リエル。
タイ国境の街ココンから船で約4時間、15ドル。
ゲストハウス村からバイクタクシーでソカビーチまで2000リエル、市場まで1000リエル。
ゲストハウスは一泊シングル3ドル〜。
1ドル=約3900リエル(2000年12月現在)
(『のまど』2001年3月号掲載)

